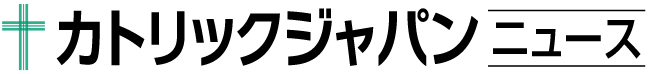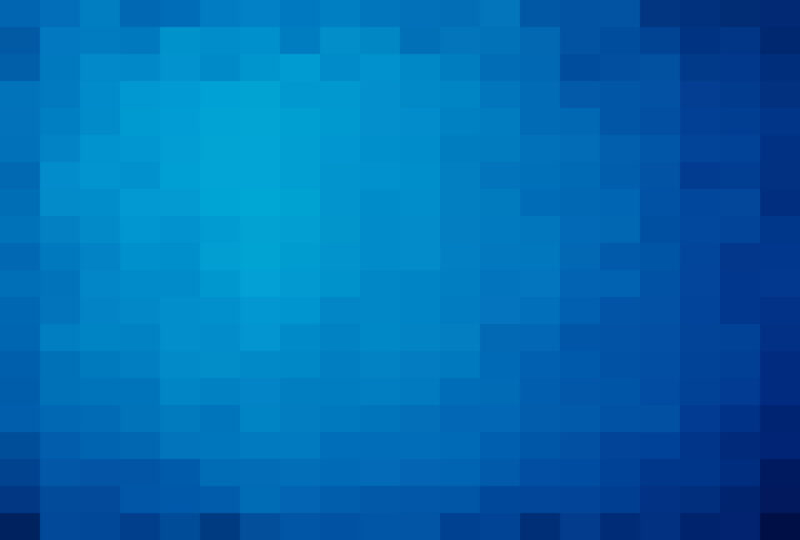かつて国教がカトリックだったフランスの〝政教分離〟(ライシテ)は、日本人がイメージする政教分離とは微妙に異なるという。
「宗教(カトリック教会)は、もう政治(私たちの暮らし)に入ってこないで!」という、民衆の叫びによってフランス革命(1789年)は起きた。その後、カトリック国としての伝統を取り戻そうとする人々と、革命の思想を引き継いでライシテを推進しようとする人々が対立。争いの中で、美術は次第に教会の権力から離れ、美術そのもので「聖性」を獲得していく。

ヤマザキマザック美術館
三重県立美術館(三重県津市)で3月22日まで開催中の「ライシテからみるフランス美術―信仰の光と理性の光」は、そうした政治と宗教の争いに影響を受けたフランス美術の歩みを辿る。出展作はミレー、ロダン、シャガールらによるフランスの油彩画、版画、彫刻など約200点(会期中、一部展示替えあり)。本展を「もっと楽しむため」の講演会が2月7日、学術協力者であり、ライシテ研究第一人者の伊達聖伸(きよのぶ)さん(東京大学大学院総合文化研究科教授)を講師に迎えて開催された。
伊達さんはまず、本展の図録が、先に開催された宇都宮での展覧会だけでなく、この会場でも既に売り切れたと知って、「ライシテは、ここまで注目されるテーマだったか?と驚いた」と笑顔で挨拶した。本展のテーマであるライシテという言葉の意味を説明し、作品写真のスライド上映を交えて、各時代の政治と宗教の関係性を解説した。
「ライシテ」とは?

展示会場では、伊達さんがライシテについて解説したプリントも配布された。伊達さんは、次のように説明する。
ライシテとはまず、フランスの歴史と結びついた政教分離の考え方のこと。国家が宗教から自律し、人々に信仰の自由や平等を保障する「法制度」であり、それを支える「思想」。異なる宗教を信じる人々と、宗教を信じない人々が共生していくための「理念」。さらに「政治権力と宗教の厳格な分離」も意味しているが、そこには「豊かな創造につながる可能性」も秘められているという。
ライシテはフランスの「国の根幹」となる重要な概念でもある。フランス憲法第1条は、ライシテの形容詞形に当たる「ライック」(教育などが宗教から独立している、非宗教的な、世俗の)という言葉を使い、「フランスは、不可分で、ライックな、民主的そして社会的な共和国である」と謳う。
「日本国憲法の前文でも政教分離のことまでは言っていませんが、フランスではライシテは国是です」
フランス革命から誕生した共和国の標語「自由・平等・博愛」に、近年は「ライシテ」を加えようとする動きも出ている。
「政治家は、ライシテは『宗教を信じる自由であり、信じない自由』『共存の原理』などとアピールしています。しかし批判的に見ると、ライシテという考え方が、ムスリムや移民に対して排他的に働くこともある事実は否定できません」
フランスでは近年、ライシテはムスリムのベールと結びつけられて語られることが多い。2024年のパリ五輪では、ライシテの名の下に、フランス代表のムスリムの女子選手が、ベールの着用を禁じられた。ライシテは「ムスリム排除の道具」などと批判されることもある。
だが現在のような「ライシテ言説の氾濫」は、長い歴史の中では比較的新しく、共和国のアイデンティティの揺らぎを反映しているという。
新しい宗教性
ライシテという言葉は、18世紀のフランス革命期以降に生まれた。革命後、政治権力は宗教からの自律を獲得し、宗教は次第に「私的な領域」へと「再配置」されていった。
そうした中でも、ナポレオン政権は19世紀初頭、カトリックはもはや国教ではないが、プロテスタントとユダヤ教と並ぶ「公認宗教」と定めた。
一方、「共和派対カトリック」という構図が、革命後のフランスの基本図式だった。教会指導者や教会組織が政治や国家権力に強い影響力を持つことに反対する「反教権主義」は、ライシテを特徴づける柱の一つだった。政府は1880年代の教育改革で、宗教的道徳に代わる「ライックな道徳」を導入。1905年の政教分離法は、共和国が信教の自由を保障するとともに、いかなる宗教も公認せず、資金援助もしないことを定めた。
こうしてライシテは、今のように形づくられていった。
ライシテを生んだ時代の大きな変化は「宗教の時代から世俗の時代へ」と表現することもできるが、宗教性がなくなるという意味ではないと伊達さんは強調する。むしろ、この展覧会で分かるように、芸術に触れたり、作品を創造したりすることを通じて人間の中に残るものを「宗教性」と捉えるのは妥当だろうと考える。
「世俗化は、新しい宗教性を生み出すことに関わっているのではないかと思います」
伊達さんはまた、『政府によって維持される礼拝の自由』(1802年頃)など、油絵や風刺画を見せながら、政治と宗教が時に激しく対立し、時には支え合いながらライシテを育んできたことを紹介した。

映しながらライシテが紹介された
情熱は時代の制約を超える
鳩は、聖霊や、平和を告げる存在として聖書に登場する。本展では、教会が大切にしてきた〝ハトのイメージ〟が、あらゆる人の心に受け入れられるきっかけとなったパブロ・ピカソの『鳩(はと)』(1949年)も展示されている(2月15日まで)。
作品の解説文によれば、ピカソは第2次世界大戦中の1944年にフランス共産党に入党後、芸術を通じて党の平和運動に関わった。旧約聖書のノアの方舟(はこぶね)の話から、ハトは長く宗教的な文脈の中でだけ平和の象徴になっていた。だが共産党の国際平和会議のポスターの絵を探していたルイ・アラゴン(詩人・小説家)は、このピカソの作品を見ると「平和の鳩」としてポスターに採用。以後、ハトは世界中のあらゆる平和運動の中で、また聖俗どちらの文脈でも用いられる国際的な平和の象徴となっている。
地元の津教会(津市)からこの展覧会を訪れた奥村豊神父(京都教区)は、こう話した。
「聖性というものは、世俗的なものを乗り越えて伝わるのだと感じました。人はそれぞれ時代の制約を受けますが、内なるパッション(情熱)に突き動かされて聖なるものを求め、表現しようとして、それが作品として結実する。作品を見ながら、描いた人の意識を超えて働く何かがあると感じました」

ピカソの『鳩』(1949年、町田市立国際版画美術館)
2月15日、3月14日は、担当学芸員が本展と関わりの深いテーマについて、スクリーンに展示作品等の画像を映しながら話す(40分程度)。詳細は、本展のサイトから。
★チケットプレゼント★
本展(三重)のチケットを5組10名様にプレゼント致します。ご希望の方は、はがきに、名前、郵便番号、住所を明記の上、〒135-8585東京都江東区潮見2の10の10 カトリックジャパンニュース「ライシテからみるフランス美術―信仰の光と理性の光」係まで。2月20日(金)当日消印有効。賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

しい」と言うロドルフ・ブレスダンの版画『善きサマリア
人』(1861/1867年、三重県立美術館)。サロンに出品され
た際のタイトルは『キリスト教徒を救うアブド・アルカーデ
ィル』。1860年中東でムスリムの一派が反乱を起こした際、
かつてフランス軍と戦ったアルジェリアのムスリム指導者
がキリスト教徒を保護した出来事に触発され制作した作品