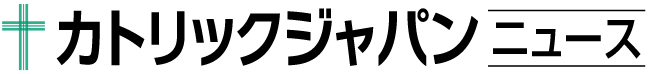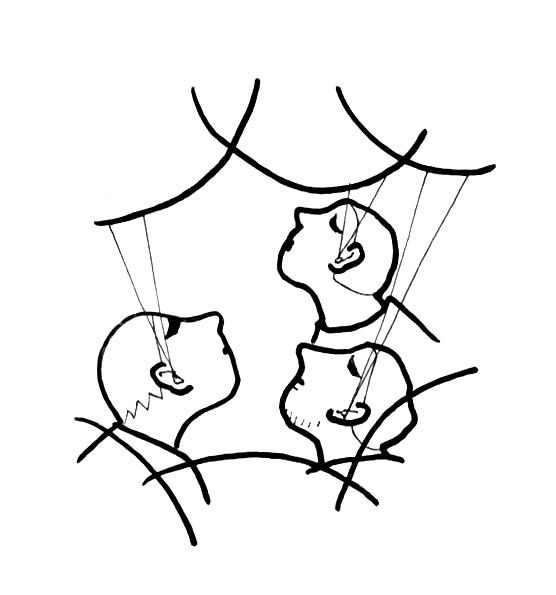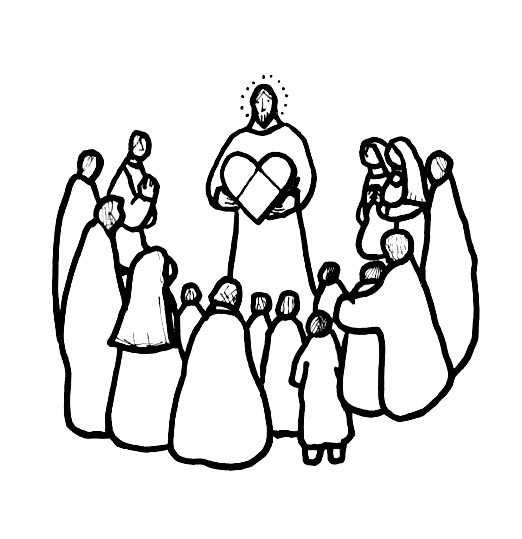占星術の学者たちは星を見て出発の決意を固める。ベツレヘム到着後は、幼子と出会い、贈り物をささげ、夢でお告げを受けた後、予定とは違うルートで帰国する。学者たちが頼りにしたのは夢であり星である。今の私たちが大きな決断をする際、これらを頼りにすることはほとんどないであろう。人間は夢も見れば星も見る。しかし、われわれにとってその映像や輝きは文字通り夢まぼろしのごときものであり、流星のごとくあっという間に視界から遠ざかってしまうものであり、当てにはならないものなのである。そう考えると、東方の学者たちをこれほどまでに強く突き動かしたものとは一体何だったのかと考えざるを得ない。
まず最初に気付くのは、天体の動きを見極めようと日夜研さんを積んでいたとはいえ、彼らは全てを分かって出発したわけではなかったということである。ベツレヘムへ到着する前、エルサレムに立ち寄った学者たちはヘロデ王に向かって次のように質問する。「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか」(マタイ2・2)。彼らは確証もなく自信もないまま、祖国を後にし、救い主を拝むために出かけたのである。
次に注目したいのは、学者たちの探している「ユダヤ人の王」は彼らにとっては外国人だったという当たり前の事実である。当然にして、これこそが「公現」にとって欠くべからざる要素であり、イエスが諸国民、諸民族の王として誕生したことを象徴的に物語る出来事なのであるが、学者たちがよその国の王を拝むために決行した危険な旅は、現代的感覚からすれば驚くべき冒険に映る。
そして最後に注目したいのは、彼らは幼子に会った後ではなく、会う前に喜びにあふれていたという記述である。マタイは次のように記す。「学者たちはその星を見て喜びにあふれた」(同2・10)。彼らが救い主を見る前に「幼子のいる場所の上に止まった」(同2・9)星を見て喜んだという描写は、これが信仰の旅であったことを類推的な仕方で想起させる。
こう見てくると、確かな証拠もないまま、しかも外国人の王を拝むために旅をし、イエスに拝謁する前に喜びを先取りしている占星術の学者たちの思いが、幾らか垣間見えてくるようにも思われる。
彼らはつまり、誰よりも救いを必要としていたのではないか。現状に喜びは少なく、今の自分は救われていないと強く感じていたからこそ、救いを求めて、いさぎよく祖国を旅立つことができたのではないか。「ここに」救いがなかった故に、思い切って「よそに」行くことができたのではないか。星が止まった時、彼らは自分たちのつらく長い旅が終わったことを悟る。もうこの下に、「ここに」救いがあると確信したのである。
顧みて、われわれをイエスとの出会いに導くのも、始まりは失意や悲しみであり、真実なものへの飢え渇きなのではあるまいか。さらに言えば、闇であり、絶望の淵をさまよい歩くことであり、総じて救いのない日々であり、そして、その中で小さく輝く信仰の光なのだろうと思う。
(熊川幸徳神父/サン・スルピス司祭会 カット/高崎紀子)