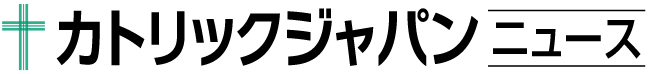ハンセン病患者とされた男性が殺人の罪に問われ、一貫して容疑を否認しながら死刑となった「菊池事件」。その再審の可否が1月28日に熊本地裁で示されるのを前に、事件を基に作られた映画の上映会が各地で開かれている。
東京・千代田区の麴町教会でも1月10日に行われ、会場は165人の参加者で埋まった。映画と関係者の話は、ハンセン病への偏見と差別が事件を生んだことを改めて浮き彫りにした。主催は「菊池事件の再審実現をめざす東京連絡会」。「カトリック東京正義と平和の会」「高麗博物館 ハンセン病と朝鮮人研究会」などが共催した。
菊池事件は1950年代初め、熊本県北部の村で起きた。村役場の職員だった男性が殺害され、その職員によって熊本県にハンセン病と通報された同村のFさんが容疑者に挙げられた。裁判は国立ハンセン病療養所・菊池恵楓(けいふう)園内の隔離された場で行われ、十分な弁護活動が行われずに死刑が確定。62年に執行された。この裁判については、熊本地裁が2020年、「法の下の平等」を定めた憲法14条などに違反すると判断を下している。
上映された映画『新・あつい壁』には、菊池事件関係者の証言を基にした場面が数多く登場する。
Fさんが逮捕時に警官に銃で右腕を撃たれた後、激痛に苦しみながら格子越しに取り調べを受ける様子や、書記官として裁判に立ち会った司法関係者が後に「私たちは(Fさんを)一人の人間として扱わなかった。ボロ雑巾のように扱ったのです」と告白する場面も描かれる。Fさんとの関わりを隠す親族の行動からは、差別への強い恐れが伝わってくる。映画は、現代の若いルポライターが過去の事件を取材する形で展開し、現代にも、ハンセン病患者の家族であることを話せない苦悩が存在することも描き出されている。
製作者の中山節夫監督は菊池恵楓園の近くで育ち、幼い頃から「差別を植え付けられてきた」と言う。中山監督は菊池事件について、あいさつの中で、「ハンセン病への偏見差別」が人の命を奪った事件だと述べた。
再審弁護団の金丸哲大弁護士は、有力とされてきた証拠についての問題点を具体的に挙げ、この事件をえん罪事件とする理由を説明した。
上映会の最後に、ハンセン病元患者家族の一人が、顔と名前を公にしない条件で登壇して思いを伝え、最後にこう訴えた。
「私は子どもの頃の経験から、他人には、親きょうだいがハンセン病だったことは見ない、言わない、聞かないこととしてきました。でも家族訴訟に参加してからそれが間違いだったと気付きました。誰かが言わなければ、世間にはなかったことにされてしまいます。ハンセン病だったことを堂々と言える社会にしたいのです。ハンセン病(を巡る問題)を風化させてはならないと思います。再審請求が認められることを祈りつつ、『思いよ届け』と訴え続けます」
上映会に参加した細渕則子修道女(マリアの宣教者フランシスコ修道会)は、「人を人として認めないところから問題や事件が起こっていることを強く感じました。同様のことはさまざまな形で今も起きています。福音に照らして、『それは絶対におかしい』と指摘する教会、社会となることが大切だと思います」と話していた。