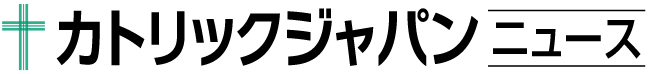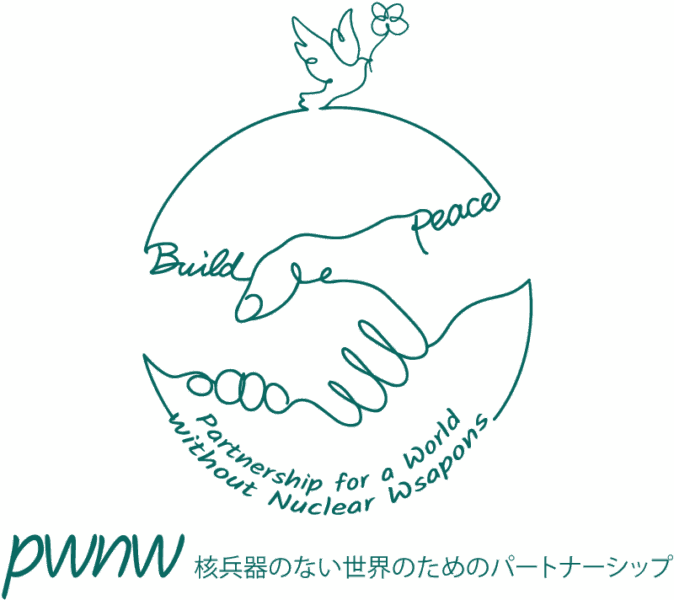栃木県那須塩原市にある学校法人「アジア学院」(校長・荒川治)は、農村共同体のリーダーを世界に送り出してきた全寮制の専門学校だ。キリスト教精神に基づいて1973年に創立されて以来、アジア、アフリカ、中南米などから、自分が生活する地域の問題・課題に気付いた「草の根の農村指導者」たちを学生として招き、9カ月間のリーダーシップ(指導者)研修を英語で行っている。
コミュニティーのメンバーは学院のスタッフと学生を合わせて60人ほどで、互いに名前で呼び合い、祈りの時を共にし、分かち合う。共に畑を耕し、一日3度の食事も掃除も共にする。そして、互いが持つ知識や経験、学びへの関心、さらには個人的な課題も持ち寄り、分かち合う。両者は〝教師と生徒〟という関係にはなく、いわば生活共同体だ。
研修が終わる12月上旬、アジア学院を訪ねた。そこには愛故に弟子たちの足を洗ったイエスのように、いのちに奉仕をする「サーバントリーダーシップ」の価値に目覚めた学生たちがいた。
コミュニティーの中心は、食堂棟
アジア学院は、JR西那須野駅から車で約10分、新幹線が止まるJR那須塩原駅から車で約20分の、森林や畑に囲まれた丘の上にある。
学院の皆のキャンパスであり生活空間でもある約6ヘクタール(60,000㎡)の敷地は、性質上、大きく三つのエリアに分けることができる。①「コミュニティーの中心」として位置づけられている食堂棟「コイノニア」(ギリシャ語で「交わり」を意味する)や、毎日「朝の集い」で使うチャペルや教室棟などのあるエリア、②コミュニティーメンバーの食料を生産し、かつ農業とリーダーシップの実践の場所でもある「農場」、そして③男女別の「寮」エリアだ。

たち。コミュニティーの中心である食堂は、
学生の入学式や卒業式の舞台にもなる
つながりと循環の中で生きる
2025年度は17カ国から本科生27人(うち日本人2人)、研究科生2人が研修に参加。取材で訪ねたのは、12月中旬に出身地に戻る学生たちが9カ月間の実りを確認し合う時期だった。
12月3日、学生たちはいつものように「コイノニア」で昼食をとった後、隣接する教室で、学びの成果をグループごとに発表した。発表の中には、販売する手立てや情報のなかった有機農産物の生産者と業者、消費者をつなぐマーケティングや、学院の畑で使用している有機肥料「BOKASHI」(ぼかし)の普及・啓発をテーマにした寸劇による発表もあった。

扱う業者(左端)に向けて、その肥料の有効性を
力強く伝えた。写真中央は、農民たち
有機ぼかし肥料とは、米ぬかや鶏糞(けいふん)などの有機質原料を微生物の力で発酵させた自然由来の有機肥料のこと。
学生による前掲の二つの寸劇によれば、開発途上国の農業生産者は、「化学肥料を業者から購入しなければ、農業はできないと思い込んでいる」ことが多いと分かる。貧しい生産者は、化学肥料や農薬を購入し、経済的負担に苦しみながら農業を続けていることがある。生産者も農作物を扱う業者も、農薬による健康被害を知らなかったり、被害を知りながら、従来の生産方法を変える手立てのないまま〝貧しい農業〟を続けていたりする。
アジア学院の学生は皆、そうした環境下で生まれ育ちながら、現状に問題意識を抱くようになった人たちだ。地元で農村開発を行うNGO(非政府組織)などに見いだされ、推薦を受けてアジア学院で学んでいる。そして、例えば研修でぼかしの存在を知り、実際に作り、自ら使用する中で、自身も含めて全てのいのちがつながり合い、循環の中に生きていることに気付いていくという。
この日、学院内を案内してくれたスタッフの荒川朋子さん(前校長)は、「学院では敷地内の裏山にご飯を入れた竹筒を埋めて、微生物を集めるところから肥料作りを始めている」と話していた。

学院の土、そして加熱し臭い等が抜けた状態の鶏の糞
(ふん)などを混ぜたものが、毛布の下にねかせてある
学院の土と微生物によって生まれたぼかしは、学院の畑を豊かにし、学院関係者が食べる食物を生み出す。食材は調理などの過程で一部が残飯となるが、残飯も堆肥化して再び土に戻し、土壌を豊かにしていくという循環を生んでいる。その循環の中で生活している学生は、わざわざ化学肥料を購入する必要がないことがはっきり分かるのだ。
先の寸劇は、多少の照れ笑いを交えながらの発表だった。しかし体験に基づく確信があるためか、ぼかし肥料の有効性が力強く語られた。貧しい生産者が持続可能な農業へ踏みだせるよう力づけ、後押しする方法も端的に示された。そして劇は、互いにつながり、気付きを得た生産者など、登場した皆が笑顔になって締めくくられる。
発表後、かつて学院の学生で、スタッフだった時期もあるインド出身のアチボさんは、近く巣立っていく学生たちに「地元で小さなアジア学院をつくってほしい」と話していた。
贖罪の思いから始まった
アジア学院の前身は1960年代、日本基督教団を母体とする東京・町田市の「農村伝道神学校」に設置された「東南アジア科」だ。アジア太平洋戦争(1937~45年)において日本のキリスト教諸会が戦争協力に加担したことに対する贖罪(しょくざい)の思いを込め、「東南アジア諸国の諸問題を解決に導く農村指導者の養成」を目的に開設された。
73年、東南アジア科は同神学校から独立し、現在の地に、地元の人たちの献身的な功労によって土地を得てアジア学院として開校された。東南アジア科で実践神学を教えていた学院創設者・髙見敏弘さん(1926~2018年)の下、第1期生として6カ国からの16人(うち日本人は6人)が学び始めた。
現在、卒業生の出身地は世界62の国・地域に広がり、人数は1445人に上る。

数は1445人、世界62の国・地域に広がっている。
近年は学生の半数以上をアフリカから受け入れるようになった
理由は「シンプル」
学院の生活は、毎朝、グラウンドでのラジオ体操から始まる。午前中は、施設内外の掃除をした後、各自担当する畑や鶏の世話、飼料作り、食事作りなどを行う。学院のカリキュラムの柱の一つ、自然と調和し、自活力を養う「フードライフ」の研修だ。

でえさをひなにやった後、飲み水の容器を洗う学生たち
朝食を終えると、午前9時半からチャペルで、学生やスタッフが持ち回りで1人ずつ、自身の問題意識や信仰など大切に思うことを分かち合う朝の集いを行う。その後、午前の授業がある。
昼食後は、午後1時45分から授業、そして夕方のフードライフの作業と続く。
夕食は午後6時半から。その後は教室棟など、お茶を飲むことのできるスペースで語り合ったり、寮に戻ったりと自由に過ごす。寮は男女別で、出身地の異なる学生2人で一つの部屋を使う。

降らない地域から来ている学生も多く、踊ったり歌ったり、
雪の中、お互いに写真を撮り合ったりしていた
学生たちの出身地域は多様で、信仰する宗教や文化、生活習慣も異なる。それでも共同生活が成り立つのは、なぜなのか。新潟教区・糸魚川教会を拠点に司牧をしながら、1年ほどアジア学院で研修を受けてきた伊藤幸史神父(新潟教区)は、こう話す。
「シンプルなことですが、自分たちが食べる物を、汗を流して一緒に作り、一緒に食べているからではないでしょうか。『食』は私たちのいのちを支える根本です。その根本でつながっているから共同生活が成り立つのです。イエス様が最後の晩餐(ばんさん)をはじめ、『食』を大切にされた意味を深く考えさせられます」

自分たちでつくったもので、食事も3食、自分たちでつくる
「初めて信仰を分かち合えた」―マディさんの話
学生の一人、フィリピン出身のマディさんは以前、中東のクウェートやイラクで11年間出稼ぎしていたと記者に話してくれた。「妹たちの学費のため、家族に仕送りをしていました」
帰国後、移住者を支援するNGOとつながり、学院へ。「貯金をする概念もなく、仕送りに頼ってしまう家族」の在り方に苦しんだ経験から、そうした家族への啓発や、持続可能な生活を普及するためのスキルを学ぼうと学院での生活に取り組んだ。

ニンジンを洗うマディさん(写真奥中央)。皆が耕した
畑のニンジンは、どれも伸び伸びと育って大きいもの
が多い。形も不揃いが当たり前で、皆、笑顔になる
マディさんは言う。「ここで得た最も大きな学びの一つが、サーバントリーダーシップです。上から指示をするのではなく、奉仕をするリーダー。中東や、フィリピンにいた頃にはなかった視点です」
持続可能な社会を実現していくのは、〝トップダウン型〟ではなくメンバーの声や存在を尊び、周囲の状況に配慮する存在なのだと実感した。
そして、「私に大きな変化をもたらした活動の一つが、チャペルでの朝の集いでした」と話す。
マディさんはここで「(自身とは宗教が異なる)仲間の信仰に触れ、神がどう人生に働きかけるか」に気付いた。そしてカトリック信者として、自分の信仰も初めて分かち合えたのだと、こう話した。
「フィリピンではしたことのない、すばらしい体験でした! 私がこうして神様に本当の意味で出会うことができるよう、それまでの全てのことが用意されたのだと、今は感謝しかありません」

カトリック司祭アンソニー神父(写真中央)は、農場で学
び、司祭として召命が新たにされた喜びを分かち合った
「その人らしさ」が輝く研修
12月4日午後の授業は、世界中の卒業生とつながり、支援している米国人スタッフのスティーブンさんが担当した。
研修後、学生が人々に奉仕しようと夢を抱いて帰国しても、地元の人から「日本へ金稼ぎに行った」と誤解されるばかりで苦悩する時期が続くことがある。スティーブンさんは、これまでの卒業生が体験した苦労や工夫の事例も交え、傷つきながらも立ち直っていくための術を学生たちに教えた。
学生たちは、小グループごとに「(帰国後)あなたが直面する試練とは何か」についても話し合った。
あるグループでは、内戦で地元に無事に戻ることが難しいというミャンマー出身の学生が、紛争のために帰郷のルートを見つけられずにいたコンゴ出身の学生に、「まずあなたが無事であることが大切。時間をかけて(帰郷して)ほしい」と話していた。

立ち寄り、学生たちの話を聞くスティーブンさん
この日は、研修の総括として複数の学生が発表を行った。学生たちは研修で学んだサーバントリーダーシップによって地域の人々に奉仕していきたいと語り、そのための具体策を披露した。
ガーナでコミュニティーの土地紛争に関わり、民族間の結束を促進させるために活動していたフランクさんは、「若者を力付け、持続可能な農業と農村コミュニティーの発展へ」というテーマで発表。ぼかし肥料の有効性などについて啓発し、教会との連携、そして若者や女性、障害者らの包摂も進めることによって食糧を増産し、収入を創り出すプランを披露した。
発表会に、生後3カ月のわが子を抱いて夫と共に駆け付けた育児休暇中のスタッフの金森郁美さんは、笑顔でこう話した。
「9カ月間の学びの実りや、学生たちの変化も感じましたが、むしろ学院に来た当初から持っていたその人らしさが際立って(輝いて)いて、『ああやって人々の前に立ってやっていくのだろうな』と思えました」
アジア学院では今、世界の農村コミュニティーに「平和と希望の光」を届けようと、開発途上国から来年迎える学生の学費を支援するための「クリスマス・冬の寄付キャンペーン」を行っている。詳細はアジア学院ウェブサイトへ。

発展へ」というテーマで発表するガーナ出身のフランクさん