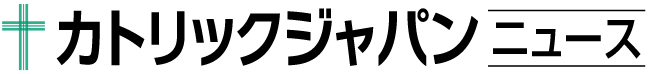昨年12月28日、茨城県結城市の施設、上山川就業改善センターで、恒例の「茨城ダルク餅つき交流会」が催された。主催した茨城ダルク(同市上山川)は、民間の薬物依存症回復施設。真冬の澄み切った青空の下、ダルクのメンバー30人余りと支援者、近隣の住民ら計80人以上が集い、交流するひとときを楽しんだ。

ダルクの仲間や、参加した子どもたちも見守る
20年ほど前から、コロナ禍の時期を除いて毎年開催されている餅つき。以前は茨城ダルクで行っていたが、近年は参加者が増えてきたため、同センターで開催している。
今回は、もち米約60キロを用意した。ダルクのメンバーが三つの羽釜(はがま)でもち米を蒸し上げ、順次、臼の中に移すと、他のメンバーや来場者有志が「きね」でついていく。誤って、きねを臼の縁に振り下ろしてしまったメンバーがいれば、「そこ、餅ないよ!」と間髪を入れず〝突っ込み〟を入れるメンバーもおり、参加者の間に和やかな笑いが広がった。
様子を見ていた未就学児が周囲の手を借りながらゆっくり餅をつき始めると、見守っていた大人たちも頬を緩め、「よいしょ!」という掛け声で応援する。

ダルクのメンバーに教わり、餅つきに挑戦した
埼玉県上尾市に住む新垣暉子(しんがきてるこ)さん(82)は歩行が不自由だが、友人に誘われ、手押し車を押して参加した。「最初は(餅つきを)遠慮していたけれど、やってみたら、臼の真ん中に(きねを)入れるのが楽しかったわ」と振り返った。
この餅つきに20年来、参加してきた鈴木勇さん(結城市在住)は、今年も地元の〝ベテラン世代〟として、きねの振るい方や、餅つきの楽しみ方を参加者に指南した。鈴木さんが臼の周りに子どもたちを呼び集めると、そばにいたダルクのメンバーが、羽釜から移した後のきねでつく前のもち米を一口分ずつ子どもたちに配った。そして口に入れたもち米を無言で、大切そうに味わう子どもたちに目を細め、「おいしいでしょ?」と声をかけながら、こう続けた。
「昔の子どもは(大人が餅をつくのを周囲で見ているだけだったけれど)、みんなこれが食べたくて集まっていたんだから」

もち米を載せ、地域の住民(右)が塩を振った
鈴木さんがさらに、「〝元・子どもたち〟も、おいで!」と呼びかけると、ダルクのメンバーや保護者も寄ってきて、それぞれ手のひらに一口サイズのもち米を載せてもらい、口に運んだ。その味わい深さに自然と笑顔になり、お代わりをする人がいた。
臼を囲んでにぎわう人たちを日なたぼっこをしながら眺めるダルクのメンバーや、おしゃべりを楽しむ参加者の姿もあった。
みんな、「神様の手の中にいる」
DARC(ダルク)は、1985年に東京で始まった民間の薬物依存症回復施設。毎日、朝昼晩のミーティングを行う共同生活を通して、依存症からの回復を目指す共同体だ。
創設の土台には、長年、薬物・アルコール依存症者の回復を支援した故ロイ・アッセンハイマー神父(メリノール宣教会)の活動や関わりがある。ダルクを創設した故・近藤恒夫さん(日本ダルク前代表)や茨城ダルク代表の岩井喜代仁(きよひろ)さんは、活動を通してカトリック司祭と出会い、洗礼を受けている。
現在、ダルクの施設は全国に64カ所ある。茨城ダルクを含む多くのダルクは、教会関係者に限らず広く一般に開かれた「日本カトリック依存症者のための会」(JCCA/会長・谷大二〈たにだいじ〉名誉司教)の加盟施設でもある。
茨城ダルクは1992年、現在の地に開設された。
現施設長の水ノ江淳(あつし)さんによれば、当初は地域住民による反対運動などもあったが、少しずつ受け入れられるようになったという。そして鈴木さんら「ダルクとつながろうとしてくれた人たち」と共に始めたのが、この餅つきだった。
「メンバーの中には、(つながろうとしてくれた)地域の方に、誠意をもって応えたいという思いがあったのです」
近年、茨城ダルクの入寮者は、アルコール依存による身体的な疾患を抱える人や、複数の障害を抱える人が増えた。高齢化も進んできたため、従来の回復プログラムをこなすことの難しいメンバーが増えている。そこで、こうしたメンバーが「ゆっくりとしたペースで」回復に向かうことのできる新しい施設として、昨年6月、茨城県石岡市に「リカバリーハウス」を開設した。
現在の茨城ダルクとリカバリーハウスのメンバーは、それぞれ17人。今回の餅つきは両施設のメンバーが一緒に地域の人を迎えるイベントとなり、最後は恒例の和太鼓の演奏が披露された。

奏者の中には、3年前に退寮した元メンバーもいた。今も「仲間の必要」を感じ、ダルクの行事に参加するなど、自分なりにメンバーとの関わりを保ちながら薬物を使わない生活を続けている人だった。

最前列で「一人一人の魂を込めた迫力の演奏に、心と体で聞き入った」という参加者の一人(70代)は、こう話した。
「今日は、聖家族の日。ダルクの方や参加された方、皆さんそれぞれの思いや言葉、まなざしに触れました。同じ釜の〝餅〟を食べたみんなそろって、目に見えるかたちで神様の手の中にいる共同体だな、聖家族だなぁと感じました」